Fumio Sasaki's Blog, page 5
July 26, 2020
エンプティ・スペース 017 夕涼みの風景 東京ローカル 沼畑直樹Empty Space Naoki Numahata

2019年9月2日
9月1日、日曜日に朝市に行った。朝市といっても、昼の3時からはじまる朝市。ローカルの人々が集まり、小さな店舗が集うお祭りだ。
前々から友人が出店している縁で通っていたが、今回は引っ越した先の近くで行われるので、「絶対行くよ」と参加を表明していた。
昼の3時開催になったのは、暑いからだ。私も土曜日に熱中症になり、夏のピークは過ぎたとはいえ、まだまだ昼間は危険だった。
なので、日曜日の昼ごろから家でクーラーをつけて家族で映画を観ていて、すっかり朝市のことを忘れていた。
仕事仲間で近所に住むHachiから4時ごろ電話があり、朝市が今日だということに気づく。
急いで支度をして、5時ごろに家族三人で家を出た。
小金井の住宅街の真ん中、知らなければ誰も来ることがないような場所にある、丸田ストアという2階建ての古く小さな建物が今回の朝市の舞台。
出店しているのは、友人のガラス工房ニジノハと、ちょうどウルウルというサイトで取材させてもらった陶芸デザイナーの岡田ちひろさん。
そして、丸田ストア内にあるお菓子屋スプーンフルや、地元の珈琲屋である出茶屋さん、アカシヤベーグルさんなど。
妻にはアウェイ感があったかもしれないが、到着すると妻の仕事の先輩がいたり、先頭で出店している二人が知り合いだったり、それなりにリラックスできる環境だったと思う。
ついさっきまで人でごった返していたらしく、まばらになったタイミングも良く、食べたり、飲んだり、お花を買ったり、のんびりと過ごすことができた。
丸田ストアの中には路上に面した広い飲食スペースがあり、時間が経つにつれ、そこの紅い室内灯が目立つようになってきた。
ちょっと一息つこうと、道の向こう側に立って、ストア全体の風景を見ていると、この雰囲気はどこかで出会ったことがあるな…と思った。
[image error]
思い出してみると、
1. 新宮の夕涼み風景
2. 京都の住宅街、ある銭湯の前の夕方
に似ている。
新宮は、紀伊半島の東側にあり、果ての果てにあるような町。京都の住宅街は、観光地ではない、普通の住宅街。
どちらも、夕方に人が外に出て集まっているという、今だと祭りのときにしか見ないような光景(自分にとっては)だった。
丸田ストアには人が集い、店ではかき氷をせっせと作っている。
夕方になり、涼しさもある。
20代のころ、新宮を舞台にした中上健次の『千年の愉楽』という本が好きだった私は、その町を歩いてみたくなり、新宮を一人旅していた。
夕方、町の中心街を歩いていると、それは吉祥寺を歩くという感じではもちろんなくて、たとえば下駄をはいた父と娘が歩いていて、少し暗くなった小さい町に、電灯が灯りはじめる…という感じだった。
人々が家を出て、夕涼みしているように見えた。
私の今の家のまわりでは、近所の人たちが夕方にわらわらと出てきて涼むということはない。
人々はたぶん、スーパーには行くかもしれないが、路面店の八百屋やスーパーではなく、大きな建物のスーパーに行くので、お祭り感なんてない。
京都でも同じような光景を見た。
旅の途中で日が暮れて、住宅街をとぼとぼ歩いていた。目の前に銭湯があり、そこに家族が入っていく。
もう記憶が薄れてあいまいだが、お店(路面店)が並ぶ商店街だったかもしれない。
台湾の映画『クーリンチェ殺人事件』にも夕方や夜に人が集まる風景が出てくる。主人公が女の子を刺すシーンの背景は、紅い街灯と屋台につられて、人々が集う夜だった。
吉祥寺の商店街の中にあったが、そんな光景はなかった。
来ているのは外の町から来ている人々で、地元の人や家族がサンダルで歩いていたりしない。
私も家を出るのに、いちいち着替えて、靴を履かなくてはいけない。
「ちょっと夕涼みに出ました」ということはなかった。
地方の町や、商店街には、サンダルや下駄、もしくは銭湯帰りの格好で町を歩ける優しさがある。
丸田ストアの風景は、そんなローカルの優しい夕方の風景だった。
July 9, 2020
ヤマザキOKコンピュータ『くそつまらない未来を変えられるかもしれない投資の話』〜金より大事なものを守るための投資〜 佐々木典士
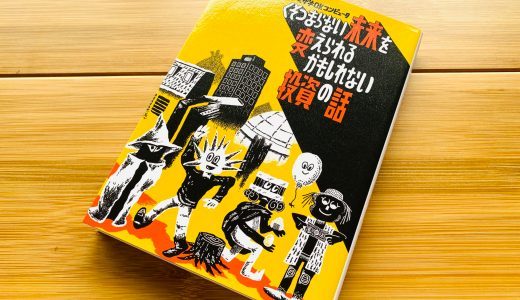
著者のヤマザキOKコンピュータ(さん付けも違和感あるし長いので愛称のヤマコンで)とは、「ぼく習」を出版する直前ぐらいに大阪で一度会ったことがある。「途中でやめる」の山下陽光さんがつないでくれたご縁だ。サバイブというメディアで書かれている記事もイラストも面白かったし、パンクと投資という一見相反するように思える要素が同居していて興味を惹かれた。ヤマザキOKコンピュータというペンネームも気が利いている。
投資という言葉が持つイメージ
もう10年以上も前のこと、芸能人を撮影する仕事をしていた時、ロケバスの中でメイクさんと投資の話になった。そのときメイクさんは投資家たちを「要するに虚業だよね」と一蹴していて、その時の自分も大体同じような考えを持っていたと思う。あなたや私の仕事も虚業かもしれないという考えが頭をかすめたが仕事をスムーズに進めたかったのでそのアイデアは話さずにおいた。
この本のメインテーマは、いかに投資を普通の人々が日々行う行為として取り戻すかということである。しかし一般的に投資のハードルは高く、投資家という言葉が持つイメージもネガティブかもしれない。ヤマコンもこんな風に言っている。
投資家という肩書きで活動していると、面と向かって、ずるい、汚い、などと言われることもある。「金の亡者」とか「金貸して」と言われるのも慣れた。言ってる人は冗談のつもりなんだろうけど、悲しいことではある。言われてムカついたとか、そう思われてつらかったというわけではなく、自分が思い描く未来への遠さみたいなものを感じて、悲しい。
この「ずるい」という気持ちは、お金を得るための労働というのは額に汗水たらすようなものであるべきという考えから来ているのではないか。クリックひとつで大金を稼ぐ投資家、確かになんだかずるいような気がする。
投資は修羅の道?
ぼくはある日、株のディーラーと出会ったのだが、その人がまず自分の投資に対するこの偏見を打ち壊してくれた。株のディーラーとして働く人は多額のお金を稼げる。年間で数億も稼ぐ人もいる。しかし、その世界のトップにいる人たちはすでにお金には興味がなく、ディーラーの世界でいかにいい成績をあげて、トップに立つか日々しのぎを削っているそうだ。ジョブズが言ったように「買いたいものなんてすぐに尽きてしまう」。だから、そこまでいくと稼ぐお金というのはシューティングゲームの点数と変わらず、ただの勝敗を決めるルールだ。目的はもはやお金ではありえず、その点数がどれだけ高いかを競う天下一武道会、強そうなヤツに会うとオラわくわくすっぞの世界なのだ。
この本でも触れられているように、投資先をチンパンジーがダーツで決めるのと、株式投資の専門家が熟考の末決断して決めるのと、大して変わらないという話もある。しかし、ほんの数%でも、0.01%でも勝率を高めるために、トップのディーラーは常に情報を集めて勉強している。その友人と会うと「最近はダンボールの値段が上がっていて~」など絶対に自分が注目していないようなことを教えてくれて楽しい。
株価には本当にいろんな影響が絡むわけで、会社の情報や経済だけでなく、集団心理や、天候や、災害リスクや、国際政治なども絡むと思うと確かに終わりのない勉強の世界だ。株の世界で勝率を高めるというのは、要するに世界全体の粒子の動きを予測するために膨大な計算をするというような話なのかもしれない。
その計算の結果出す答えは、買うとか売るとかいう単純なものなので、チンパンジーのダーツ、素人のきまぐれのワンクリックと結果は同じこともあるだろう。しかし、寝る間も惜しんで世界全体の粒子の動きを計算することは、ずるくも楽でもなんでもない仕事だし、いくら稼げたとしてもぼくはやりたくない。ディーラーの世界をその友人は「修羅の道」と呼んでいた。
結局プロには勝てない世界?
なるほど、投資自体はずるくも楽でもなく本気でやろうとするとむちゃくちゃ大変だ。だから、ぼくの中ではそれは「素人が手を出しても最終的にはプロには勝てない世界」という結論でしばらく落ち着くことになった。確かに、投資の目的が少しでも利益を出すことならプロには勝てないだろう。しかし、ヤマコンが考える投資というのはそういうのでもない。ヤマコンにとって投資というのは、もっと身近な日々の行動に宿る。
ヤマコンの投資の原点は、中学校の頃、行きつけだった弁当屋がつぶれてしまったことだった。高校生になると、友人たちと他の多くの高校生がそうするように、ファミレスやコンビニに行くようになる。そのせいかどうかはわからないが、美味しい弁当を売っていた弁当屋はいつしか閉店してしまい、ヤマコンは大いに自分の責任を問う。
コンビニやファミレスはとても便利だし、クオリティが高い。久しぶりに日本に返ってきたとき、日本のコンビニは天国のようだ。コスパが良く、いろんな場所にあり、どこの店舗に行っても期待通りのサービスが受けられ安心だ。
しかしその行動は、何も考えていない楽な行為だとも言える。コーヒーを飲むためにコンビニに入るのは、何も考えずにできるが、物々しい雰囲気を出していて、マスターのおっさんが機嫌が悪いかもしれない初めての喫茶店に入るのは確かに自分の感性が問われるし、勇気もいる。その代わり最高のコーヒーが飲めるかもしれない。
銀行預金は何も考えていない行為?
そしてこれがこの本の大事なところだが、この「何も考えずに、楽だからそうする」ということは銀行に日本円でお金を預けるという行為もそうなのだとヤマコンは指摘する。
銀行にお金を預ける行為は、コンビニに入るのと同じで、どこにでも店舗はあるし、簡単だし、元本は保証されるので安心な一面もある。しかし、インフレになれば目減りするし、日本経済の先行きが怪しくなった時には、大きなリスクとなる。
先日のコロナウイルスに関する記事でも書いたとおり、ぼくはいろんなリスクに対応できるように身軽でいるつもりだが、自分の資産に関してはリスクに野ざらしで置いてしまっていたことを反省した。
そしてぼくも全然知らなかったのだが、日本のいくつかのメガバンクは過去にクラスター爆弾を製造する企業に投資をしていたそうだ。自分たちが何も考えずに銀行に預ければ、そこからさらに投資にまわされた自分たちのお金はいつしか誰かを殺す兵器に形を変えるかもしれない。これはいかん。
お金に対する汚いイメージとか「嫌儲」が出てきてしまう理由はこういうところにも一旦があると思う。一発数千万円とかする爆弾は、高いし消耗品だしで産業としては儲けやすいのだろう。利益至上主義になってしまえば、こういうところに投資するのが一番効率がいいかもしれない。銀行に預けても、そのお金がどう使われるかまではわからない、だからまともに使ってくれそうな企業に自分のお金を預ける。なるほど。
我が投資に一片の悔いなし
ここでも、まだ投資に踏み切れない自分がいる、最後のひと押しが必要だ。なぜならぼくは元々、気が散っているので頭のメモリをいろいろなものに食われたくないと思っているから。自分の資産が毎日どれぐらい増えて減ったとかを追いたくないし、一喜一憂したくもない。この本でも株価に注目するあまり、目の前のとても美味しいお寿司に集中できない残念なサラリーマンの姿が出てくる。そうはなりたくない。
それに、全ての投資家が金の亡者というわけでもない。現に、俺の投資活動のリターンはお金だとは限らない。場合によっては、投資額より減って返ってきたとしても満足なときだってある。
(前略)そもそもの目的がお金を増やすことじゃなくて、俺の余ったエネルギーを社会に参加させることなので、お金の増減はそこまで気にならない。
自分のお金の流れる先を自分で決めるという行為は人格そのものに直結していて、たとえ損が出たとしても自分で決めたことなら文句はない。
株価を気にしすぎない秘策がようやくわかった。たとえ買った株が紙くずになろうが構わぬ、我が投資に一片の悔いなし。そんな企業の株だけを買うことではないだろうか。自分が心底惚れ抜いた企業が潰れるような世界なら爆発してしまえ、という意気地だ。
投資も応援の一種
そもそもぼくもたくさんクラウドファンディングで応援してきたし、そこで提示されているリターンも目的としていたわけではなかった。友達が作っている野菜や果物を買うのは応援したいからだし、家族経営のゲストハウスに泊まると宿泊代はこの子の今月のミルク代になるのかと思って嬉しくなる。ファンがよく言う「お布施」だと思ってクリエイターにお金を払ったり、本を買ったりもする。投資の場合は、その相手先が企業になるということなのだろう。
自分が作りたい未来のために投資すること、その未来を作るのに力を貸してくれそうな企業に投資すること。必然的に利益至上主義ではなくなるし、投資だけを仕事にするわけでもない。
お金フリークの人たちだけが投資をしていたら、世の中はお金フリーク好みの社会になる。
高齢者の人だけが選挙に行くなら、世の中は高齢者に得な方向に動く。投資は選挙と同じようなものだったのだ。
ここに来てようやく、ぼくが投資をしない理由はなくなった。格安SIMも、電気会社も、行政の補助金も、世の中にはほんの少し調べて行動する余力があれば余計なお金を払わずに済むことが多い。しかしその機会を多くの人が余裕がないせいで失っているし、それを見越してこの世界はセコく成り立っている。生き馬の目を抜くような投資の世界に飛び込むのは絶対に嫌だが、不勉強なせいで誰かが傷つけられてしまうのも同じぐらい避けたい。
パンクと投資は同じもの
パンクと投資は同居しないと思っていたが、この本を読み終えたら完全に同じものだと思えるようになった。
俺が思い描くパンクというのは、よく漫画や映画に出てくる革ジャンでモヒカンのパンクスとはちょっと違うかもしれない。派手かどうかはどうでもいいし、不良じゃなくても構わない。重要なのは「Do it your self」と「Anyone can do it」の精神で、つまり自分でやるってことと、誰でもできるってこと。それ以外はなんだっていい。
有名なパンクスのジョー・ストラマーさんは「パンクロックとはつまり、全ての人類に対する模範的なあり方のことだ」と言っていた(後略)
パンクをミニマリストに変えてもぼくにはしっくり来る。
専門家じゃなくてもいいし、誰かに習う必要はない(甘い誘惑を持ちかけてくるミニマリストも投資家もたいてい詐欺師なので気をつけて)
この本で述べられているのは、要するに、お金より大事なものを守るための投資=応援なのだ。
ヤマザキOKコンピュータ『くそつまらない未来を変えられるかもしれない投資の話』
[image error]

補足
処女作には、変わらないその人の徳性やその後抱えるテーマが出るものだし、自分の考えを初めて世に問うあの感覚が思い出されてなぜか自分まで浮足立ってしまう。「ぼく習」が出たときに、ヤマコンは自分のやりたかったことがひとつやられてしまった、と言ってくれた。これは最大の賛辞だと思う。ぼくの次の本も「お金」にまつわる話にしようと思っている。この本に出てくる「払った1円あたりの満足度」ということはぼくもいつも考えているのだがそれを「満足ポイント=MP」と書かれたのには本当にやられた感があったし、引用して次の本の参考文献に載ること決定だ。うんうんと頷けるし、お前らわかれよ、という熱い思いも感じるいい本。香山哲さんの表紙&挿絵にも嫉妬。
June 29, 2020
新型コロナウイルスとミニマリスト

ミニマリストはこの状況に向いていない?
新型コロナウイルスはミニマリストの生活にどう影響するのか?
まずわかりやすいものとして、ミニマリストはこの状況に向いていないという意見があるだろう。国内外で物流が滞ったり、買い占めが起こったとき「街が間取り」「コンビニが自分の冷蔵庫」と言いながらストックをしていなければ困ったかもしれない。
以前から、ミニマリスト生活のなかでも「災害用品だけは例外」と言い続けてきた。地震のために備えている人は多いと思うが、マスクを備蓄していた人は少なかっただろうし、今後はマスクも備蓄リストに追加したという人も多いだろう。ツイッターでも生活にどんな変化が起こったか聞いてみたのだが、備蓄は少し増やしたという人が多かった。
ぼくはこんな風に「最小限」というのは試行錯誤しながら伸び縮むするものだと思っている。それは単に「すごく少ない」という意味ではない。「最小限」が新たな備蓄の分、少し伸びた。今回の影響はそういう風に言うこともできる。
ミニマリストが強い「リスク」
災害用品や食料など最低限備えた上で、ミニマリストはリスクにも強い、とも思う。普段から少ない物で工夫する生活をしているので、物が手に入らなくなったときの心得があると思うからだ。たとえば、今ぼくは洗車用のタオルを使っているが、以前は手ぬぐい1枚だけで生活していた。そちらにもメリットがあることを知っているので、もし手ぬぐい1枚で生活することになっても問題がない。掃除機も電子レンジも便利なものだが、それを使わない心地よさもよく知っている。「これがなくてはダメ」という絶対量が少なく、物に大きく依存していない。
さらに大きなリスクにも強いと思っている。たとえばぼくは、メインの住居であるフィリピンの家に今帰れないが、大した荷物があるわけでもないので大きな問題がない。このまま長期間帰れなかったとしたも、残してきた物は誰かに郵送してもらえる程度だし、あげたっていい。住んでいた家に帰れなくなっても、大して問題がないというのはなかなかのことではないだろうか。
身軽でいれば、物理的にも精神的にも新たな動きを取りやすい。日本でのコロナ禍は今のところ、想定されたような最悪の事態ではない。しかし、もっとひどく長期的に続くようなものだったとしたら、通勤を強要される会社を辞めたり、人が密集する都会から引っ越したいと思う人もたくさん出てきたかもしれない。
そんなときに生活のランニングコストを下げておき、金銭的なものが決断へ影響する度合いを下げておけば思い切った判断が取れる。物が少なければ引っ越しは簡単だから、新しい環境へ移行するハードルが下がる。ぼくで言えば、飛行機さえ飛べばいつでも日本から離れることもできる。
自給自足生活が強い「リスク」
以上のことを踏まえた上でだが、ぼくはミニマリストとはまったく正反対のような生活もとても素敵だし、いつか自分でもやるかもしれないと思っている。
よく夢想するのはこんな生活だ。山の中で自分で建てた小さな平屋。自分ひとりが食べていける小さな田んぼと畑がある。庭では鶏や山羊を飼う。猟期には鉄砲を持って鹿や猪を追う。
家を建てるのにも、農業や狩猟をするにもたくさんの物が必要だ。一方は物が少なく、一方は物が多い生活だがぼくの中ではすでに大きな対立軸とはなっていない。
自給自足に近いような生活は、今回の新型コロナウイルスのような厄災が起こったときにはむちゃくちゃに強いだろう。映画「サバイバルファミリー」はすべての電源やなぜか車までも使えなくなった事態を描く映画だったが、養鶏や養豚をし、風呂を薪で炊くような昔ながらの農家に世話になるシーンがある。そういう暮らしをしていれば物流が途絶え、電気がなかったとしても生活に大きな影響がない。猟師さんの中には、国がどうなろうが生きていけると言っている人もいるがカッコいいと思う。3年前、次に目指すのは「誰かにやってもらうことを最小限にする」ことだと言っていたが、憧れているのはまさにそんな生活だ。
依存を少なくしてみる
いつかはそういう生活をし始めるかもしれないが、その前にやりたい実験がいろいろとあった。物が少ない生活を経て、誰も友達がいないところに住んだらどうなるのだろうと京都に住んでみた。次は日本を離れてみたらどうなるだろうとフィリピンに住んだ。
物だけではなく「友人」や「母国」から離れてみたときに自分がどうなるのかを見てみたかった。必須なもの、依存するものは少ないほど選択肢は増すように思っていたからだ。
他人に任せず、自分でエネルギーを作り、食べ物を作り出すような生活もそれと同じで、依存するものをできるだけ少なくしようとするベクトルだと思う。ぼくにとっては、ミニマリストも自給自足も、ただサッカーという同じゲームをプレイするチームのようなイメージだ。ただ取っている戦略だけが違う。
だからそれを一人でやってしまう人もいる。最近知った、Rob Greenfieldという人がそうだ。彼は1年間、自分で育てた食べ物と、自然にあるものを採取して暮らしたという。スーパーにも行かず、バーで飲み物すら頼まなかった。その時の彼は、それなりにたくさんの物を持っていたか、少なくともシェアはしていただろうと思う。
そして今、彼は免許証やキャッシュカードまで切り刻み、47個のものだけで暮らしている。彼の中で一貫しているのもまた、物が多い/少ないではなく、行き過ぎた消費主義や、他人任せになってしまっている生活への疑問だと思う。
自分の資質を見極める
災害にウイルス。どんなことが起こるか本当にわからないし、リスクも短期的なもの、長期的なもの様々だ。自給自足のような暮らしは、今回のコロナのように外部が切断されたときには強いが、一方で地震や、水害や放射線の汚染など住んでいる土地自体に問題が起こるリスクには弱いかもしれない。すべてのリスクに強く、万能に対応できる生活などない。できることは、どんなリスクに備えるべきか考えた上で、自分の資質にあった生活を選ぶことだと思う。
ぼくの資質はと言えば
・物が大好き
・趣味は増える一方
・なのに物の管理は苦手
・物が散らかってたり、色が氾濫していると気になってしまう(視覚が過敏)
・物が適切に管理できていないと、自分を責めてしまう
という要素があり、これはどうやら変わりそうにない。万が一の事態を考えることも大事だが、まずはこの生理に合った暮らしをしたい。だからぼくが自給自足のような生活を目指し始めたとしても、いたずらに物は増やさないだろう。
自分の資質に根ざしたものではなく、もし流行やビジネス的なものでミニマリズムの生活をするのであれば、そういう人はいつかその暮らしから離れていってしまうかもしれない。もちろんそういうことがあってもいい。何度か言ってきたことだが、ミニマリズムは出入り自由な学校だと思っているからだ。ずっとそこにいることが大事なわけではなく、そこから卒業する人がいてもいいし、再び門を叩いてもいい学校。
ミニマルアートがそうであるように、ミニマリズムは不変のひとつの極点だ。それは、ぼくや誰かの生活がどう変わろうが変わらない。
May 16, 2020
リアルどうぶつの森 〜雑用の再導入〜 佐々木典士

宙ぶらりんに
3月初旬に確定申告のためにフィリピンから日本に一時帰国した。フィリピンではコロナウイルスへの対策が早くしかも徹底していた。3月中旬にはフィリピンで国内移動する手段があっという間に絶たれ、何をどうしても日本から戻れなくなってしまった。
なので実家の香川県で宙ぶらりん状態。こんなに長く実家にいるのは高校生以来だし、母と長い時間を過ごすのも久しぶりだ。
[image error]▲近所にあり、人がいなさそうなところを見つけて出かける。メディアの中で起こっていることと、目の前の美しすぎる風景のギャップで頭がバグる。
香川県は感染者も少なく基本的にはのんびりとしていると思う。それでもいよいよという感じになってからは、家で過ごす時間が増えた。
基本的にカフェで仕事をするので、それもできなくなった。家で仕事をしようと机を注文したがずっと来ないまま。イベントはキャンセル。手帳は真っ白。やることがない。
そこで家の仕事である。
実家は古い家なので、とても広い。
大きな仏壇があり、和室があり、庭があるような家だ。
甥っ子姪っ子がいることもあって、最近は雛人形をしまい、五月人形を出し、またそれをしまった。庭先では毎日鯉のぼりが上がっている。
[image error]▲ものすごく立派で、しまうのにも、出すのにも結構な労力がかかる。ボタンひとつでインテリアを変更できるゲームとは違うところ。
以前からすれば随分カジュアルな形になったと思うが、実家ではそういう昔ながらの行事を続けている。正月には餅をつく。花をもらえば近くの墓に備えに行く。
意味のあることをしたい、が
広い家、庭、季節のイベントに使う物。それらを適切に管理しようと思えば、膨大な労力がかかる。自分が心がけてきたミニマリストの生活とは正反対だ。物に煩わされる時間をできるだけ減らし、大切なことに注力する。
自分にとっての大切なことは、本を書くこと。余裕のある時間を使って、本を読んだりインプットを増やしたり、ちょっと変わった体験をしてそのことをシェアする。それが自分の仕事だと思っていた。
そのせいか意識が高いというかなんというか、ぼくはふとすると、「晩ごはんを食べる20分の時間を使って、毎日TEDを1本見ることにしよう」とか考え始めてしまう人間である。
ぼくの毎日の習慣は、必ず昼寝もあるし、働く時間も全然長くないが、それでも「何か意味のあることをしたい」という気持ちは常にある。
しかし、今はそれができない。時間は売るほどあっても、毎日十何時間も本が読めるわけではない。コロナの情報を深堀りしていくと、暗澹たる気持ちにもなったりする。そして、家の仕事を見つけて始めるようになった。
・草を抜く
・庭を整える
・メダカの水を変える
・野菜を育てる
・窓を拭く
・古くなった床や壁をDIYする
[image error]▲メダカ。この状況で生き物を飼うようになった人が多いというがわかる。水換えをしたり手間はかかる。
リアル版の『どうぶつの森』だ。いつもの短い帰省中なら、避けたいような雑用たち。短い帰省なら『ジョジョの奇妙な冒険』でも再読しながらゴロゴロしていたい。でも今は時間がある。季節も良かった、寒くも熱くもなく億劫ではない。
それでも長くはしない。
午前中の数時間だけ。
その代わり毎日やる。
土はストレスの避雷針
草抜きではいろいろなことを考えさせられる。まず、土にさわるということ自体が本当に心を落ち着かせてくれる。思うように出かけられず、鬱々とした気持ちも出てくることもあったが、土にさわっている間は淀むことがない。
[image error]
裸足で芝生の上を歩くと、自分の中にあるマイナスなものが足を通じ、芝生に拡散していくような感覚があるが、土に触ることも同じ。沈んだ気持ちが土を通して濾されていく。
乗り物に乗っているときと、歩くとき。移動する速度によって見える景色も目につくものも違うが、「草抜きの速度」というのもあると思った。庭に腰を下ろして草を抜いていると、様々な色をした蛙が飛び跳ね、ダンゴムシが練り歩き、ミミズも時折顔を出す。
[image error]▲広くはない庭だが、それを自分の世界とする生き物たちの生態系がある。
簡単な力で、根をブツブツっと心地よい音とともに抜かせてくれる雑草もある。「プチプチ」をつぶすように感触を楽しめる。
ところが簡単にはいかない雑草もある、地中深くに根を張り、手で抜くだけでは途中で千切れてしまう。
[image error]▲恐ろしい深さで根を張る雑草。手ではきれいに抜けない。人間の手に負えない雑草が自然淘汰で生き残ってきたのかと疑ってしまう。
それではと、草抜きを効率的にするための器具を検索してみたりする。
[image error]▲ゲームなら「草取りのかま」にこんなにバリエーションはないはずで、選択肢が多すぎるのが現実の難点という気もする。
手こずっていたが、草を「抜く」ことから発想を変えて、土を深く掘る「収穫」だと思うとまたこれが面白くなった。
草抜きで近代を追体験する
花や野菜、樹や苔など人にとって嬉しいものは残し、邪魔になる雑草は取り除く。小さな自然を征服しようとすると、近代に人間が行ってきたことを追体験しているような気持ちになった。
そもそもどれだけ雑草が生えていようが、自然はそれ自体には隙がない。ただ人間の邪魔になるものを排除しているだけで、その環境で静かに過ごしているダンゴムシやミミズからすれば草抜きも本当に迷惑な行為だろう。
雑草を育てている面白い人から聞いたことがあるが、「雑草」かどうかというのは人間が決めた基準だと言う。抜いた後に足が早い植物は、美味しく食べられたとしても市場に乗せづらい。だから野菜ではなく、雑草というくくりになってしまう。
思わずウイルスのことを考える。ウイルスと聞けばなんだかトゲトゲした厄介者をイメージしてしまうが、「ウイルスは生きている」という本によれば、すでにウイルスは我々の体の仕組みと密接に結びついている。たとえば哺乳動物が胎盤を通じて子どもを育てるのはウイルス由来の仕組みを使っている。それは、長い進化の過程で同種の生物からではなく、感染したウイルスからも遺伝子を受け継ぐことがあるという驚きの仕組みだった。
ウイルスも、他の生物同様、自分たちの数を増やすことを目的にただ生きている。それが今回はたまたま人間と競合してしまう種類のもので、人間にとっては大変な迷惑という感じだ。
人間が食べて美味しい野菜や、見て嬉しい花を守るために今回は雑草が競合した。
「意味」と「目的」から離れる
草抜きの重要な点は、やってもやってもまた生えるということだ。
[image error]▲深く耕して取りきったと思っていたのに、2日後にはすでに5cmぐらい葉を伸ばしていたりして我が目を疑う
何日かすると自分が草を抜く前の状態に戻る。だからやってもやっても終わりは一向にやってこない。すると「意味がない」ように思えてきてしまう。終わりがないものは、「意味」とか「目的」とかいう言葉とは縁遠いものだからだ。
そして、その意味のないように思える行為を切り捨てたくなる。
・長い間草抜きをしなくてもいい薬剤を使いたくなる。
・土をコンクリートで固めれば、雑草は生えなくなる。
・そもそも庭なんて手間がかかるものは持たなければいい。
そうすれば面倒な行為はしなくてもいい。その代わり土に触れる機会は少なくなり、合理的だが味気のない生活を過ごすことになるかもしれない。
個人で完結した楽しみ
自分にとっては、かつては面倒だと思っていた雑事が今は楽しみになっている。そしてその楽しみは個人で完結しているのが心地よい。
今はともすれば、いかにSNSで目立ちフォロワーを獲得し、バズらせるかというようなことを考えてしまう時代だ。誰でも「世間に一発かます」チャンスがあるのはいいが、できるだけ多くの他人を巻き込もうとする欲が透けて見えると疲れてしまう。草を抜いてもSNSで誰かに承認されるわけではなく、ただ自分だけに手応えが残る。まだほとんどの人が「ミニマリスト」という言葉を知らなかった時、部屋を整理しながら自分の身に起こった変化にひとり驚いていたときがいちばん思い出深いが、それと同じだ。
人間はやることがないということに耐えられないから、雑用でもこなすことがあるのが嬉しい。「マインクラフト」や「どうぶつの森」といった目的がなく、自分でいろいろと作業することを決めるゲームが人気だが、それは現代の便利な生活の中で無駄だと思われ切り捨てられたさまざまな雑用を、人びとがどこかで求めているのではないかと思う。
先達たちの手によってすでに舗装道路がどこまでいっても伸び、生きる仕組みが大抵完成されてしまっている日本では、開拓したり頭の中にあることを実現するという喜びも薄いと思う。『ぼくたちは習慣で、できている。』にも書いたことだが、分業が進む前は、ひとりの人間がこなす雑用、期待される役割が多く、日常を生きるだけで様々なスキルが得られ、人は自然に成長することができたのだろうと思う。
善悪は組み合わせ
今回そんな風に思えた雑用だが、以前はなぜ面倒だと思っていたのか? 善悪というのは「組み合わせ」の問題だということを以前にもブログで書いた。「時間がある自分」×「雑用」というのは組み合わせが良い。かつての自分、仕事に追われ、ストレスもあった自分ならたまの休みには雑用よりも、ゴロゴロするほうが組み合わせが良い。時間さえあれば、どんなものも楽しめるのだと知った。
新型コロナウイルスで世界中でたくさんの人が亡くなった。会社が倒産したり、仕事が立ち行かなくなった人も多くいる。一方組み合わせが良かったと言える例もある。AmazonやNetflixの株価は最高額になった。家で仕事をするのでウェブカメラや机はよく売れている。今はマスクをしているので、顔を隠すのに都合が良いということで美容整形も増えているそうだ。4月の自殺者は20%も減ったそうだが、もしかしたら救われた命もあるのかもしれない。経済が停滞している間は、環境汚染は改善した。胎盤形成に役立ったウイルスもまた哺乳類との組み合わせが良かったと言えるかもしれない。
まだ新型コロナウイルスが終息したわけではないので、自分との組み合わせの結論を出すのは早いかもしれない。書店が閉じていたり、流通が滞ったりして自分にも打撃はあり、書く本のテーマも大きく影響を受けそうだ。良かったこと、悪かったことは個人の中にもまだら模様のように存在しているのだろう。
しかし、この宙ぶらりんになってしまった時期だからこそ、意味や目的から離れたものを見直すことができた。これは誰かに配慮するあまり、自粛で塗りつぶしてしまうにはもったいない。退屈ながらも穏やかで、母と過ごしたこの長い長い時間は、振り返ってどうやら思い出深いものになりそうなのだ。
May 6, 2020
エンプティ・スペース 016 コロナ疲れ 沼畑直樹Empty Space Naoki Numahata

2020年5月7日
GWが終わった。コロナの自粛中のGWは、なんだか疲れた。
疲れたといっても、長いテレワークの続きで、どこにもでかけられなくて疲れたわけではない。
普段のリズムと違ったから、でもない。
15年前から自宅作業なので、妻がテレワークになったところで夫婦喧嘩が増えたりもしないし、7歳の子どもが小学校にいけずに勉強を教えなくてはならないから。でもない。
すべてはいつも通り。自粛前とそれほど変わりはない。
でも疲れた。
たぶん理由は、やっぱり出かけられないことなのか。
いや、晴れた日には朝早く、4時5時ごろに誰もいない公園沿いの道を走る。それだけでただ気持ちがいい。
子どもは家にずっといると視力が不安になるから、遠くのものを見られるように、車で出かけるようにしている。
車からは降りず、20分ほど走って風景を見て帰ってくる。
近くに大きな公園があるが、駐車場が禁止になると人混みが消えた。そのかわり、ジョギングする人で道が混み合うようになり、散歩をしていても落ち着かないので、公園散歩も控えるようになった。
かわりに霊園を歩いてみると、人が誰もいない。
家族でぐるぐると歩き回った。
運動としてはそれでも足りないので、家での運動を増やすことにした。意識したというわけではなく、シンディ・ローパーのグーニーズの歌を検索していたら、懐かしい『Girls just have want to fun』という歌が出てきた。
聞いているうちに、踊りたくなって、娘と飛び跳ねる。
ジャンプをし続けるというだけで、クラクラしてきた。でも楽しいので、腕を振って、リズムに合わせて飛び跳ねる。
一曲終わって椅子にもたれかかると、気持ち悪くなった。
あくまで、運動不足によるものだ…。
しかし、縄跳び以上の効果あり、散歩以上の効果ありということで自粛中の運動に採用。ジャンプもダンスも、それなりにスペースが必要になる…。
リビングにはテーブルと椅子があり、それを自由に動かすことができる。いつもは端に寄せて、運動できるスペースを大きくしているが、GWは真ん中に置くバージョンにした。自由に動かせるのは、それ以外の家具がないからだ。テレビがあったら、動きは制限される。
テーブルを真ん中にしても、なんとか運動スペースはある。
ここで、曲を流してむちゃくちゃに踊る。
約束事は、リズムに合わせてジャンプすること。それだけ守れば必ず疲れる。
ついでに、歌詞も覚えた。
英語の歌詞を覚えて歌うのはいつも楽しい。
ちなみに、80年代の強く幸せなアメリカを象徴するこの歌は、楽しい歌なのに少し泣けてくるのが不思議だ。
自由に遊ぶことを制限された少女たちが解放されるという心情と未来への希望。コロナで制限された世界の人々の希望と同じなのかもしれない。
ところで、疲れたのは、ジャンプしすぎたせいなのか。
それとも、殺菌の毎日に疲れたのか。ニュースの見過ぎか。
答えは出てないが、
They just wanna
と歌ってむちゃくちゃに踊っている限りは、その「疲れ」が心地いい。
懐かしいオフィシャルだが、この曲は別のアーティストのカバー曲。シンディの独特の歌い方によって国民的名曲になった。今もアメリカ人の体に染み込んでいる。
April 12, 2020
エンプティ・スペース 015 どこにも行かない 沼畑直樹Empty Space Naoki Numahata

2019年3月7日 ※およそ1年前に書いたものです
去年、2018年の6月に家を購入して、今は年を越え3月。その間、どこにも旅行に行っていない。
友人はニュージーランドにドライブ旅行に行った。
友人はイギリスに行った。
義理の姉は先週、ベトナムに行った。
海外はまだいい。国内旅行も一切行っていない。
「ミニマリズムの暮らしを始めると、旅をしたくなる」
というが、最近は本当に旅行というものをしていない。
これは、新しい家がまだまだ新鮮だということと、なんとなく贅沢はしないでおこうという心のブレーキがあるからだと思う。
妻も私も、旅行に行きたいと思いつつ、節約もしたい。
札幌に帰省もやめて、飛行機代を親に渡して東京まで来てもらうことになった。だから札幌旅行もない。
仕事でも海外の仕事をブッキングしなくなり、それも気持ちの問題なのだが、なぜか気分が乗らない。これはまた別の理由があるかもしれない。
「未知の世界へ旅…」という、ある車のキャッチコピーを見て、旅いいなと思うのだが、広告に出てくるような森や岬はいったいどこにあるのだろう。
他に観光客がいなくて、海の見える高台に車を止めて、テントを貼れる場所なんてどこにあるのだろう? 国内で。
あったとして、家族を置いて一人車で何キロ走ればいいのだろう。
普段の車旅行はせいぜい長野の松本あたりで、京都まで行ったことはあるが、簡単なドライブではない。
キャンプは楽しい。森の中で楽しい。でも、人でいっぱいだ。
ゴールデンウィーク、10連休にキャンプでも行こうかと妻が言う。
わかる。わかるけど、GWのキャンプ場なんて、場所の取り合いでぎゅうぎゅう詰めだ。
予約して場所が決まってるタイプは好きじゃないし。
結局は、近くの公園のBBQか、ピクニックとなる。
私はなるべく家族と過ごしたい。
その気持ちと、孤独になりたい気持ちは、仲良くなれない。
孤独が好きで一人旅をして、友人のいない島で暮らしたが、それはとんでもなく楽しかった。
一方で、友人の車に乗りながら3人ほどで大阪、兵庫、京都、和歌山、奈良、名古屋、長野、新潟、札幌と旅をした思い出も深く心に刻まれている。
もう少し子どもが大きくなったら、車での家族旅行も幅が拡がるだろう。
私にとっての未知の場所は世界中にあるけれども、近辺には少なくなった。
でも、子どもに見せたい、子どもにとっての未知の場所がたくさんある。
だから自分の旅が主役でなくなってきているのだと、書きながら納得した。
GWは、宿はとらずに日帰りでいろんなところに行こう。
予定のない旅を。
March 16, 2020
エンプティ・スペース 014 コンクリの色はミニマリズム? 沼畑直樹Empty Space Naoki Numahata

2018年12月
素敵コーヒーショップが都内で爆発的に増えてきても、牧歌的な郊外に引っ越してきた私には残念だけども無縁だ。
今思えば、吉祥寺時代はコーヒースタンドが街中に溢れていて、出現しては消え、残るものは残りと、非情な商店街の移り変わりを眺めてきた。
今は公園に囲まれてお店がまったくないような場所に住み始めたので、家でよくコーヒーを淹れて楽しまざるを得ない。
1件だけ、自転車で行けばなんとかなる距離にあるコーヒースタンドは、民家を改装した黒壁の洒落た佇まいだ。
この店のポイントは、コーヒーを待っている間に座るカウンターから、中庭が望めること。
オーナー手作りのウッドフェンスで囲まれて、床はコンクリ仕上げ。これもオーナーが自ら施工したという。
そこには植物、椅子、パラソルが揃っていて、寒い季節にそこを利用する人はいないけれど、眺めているだけで、すっとした気分になる。
清々しい気分になる理由はたぶん、床が土ではなくて、「無機質」と形容されることが多い、「コンクリ」のせいだろうか。
思い出せば、私が憧れた上小沢邸も建物自体がブロックとコンクリ、鉄筋で出来ていて、実に無機質。最新の素材で未来的にミニマルな今の住宅とは違い、古びて汚れて、決して普通に美しいわけではないのに、心を惹かれる灰色の建物。
最近、よくこの建物に出会ったときの感触を思い出していて、それが掲載された古本を注文してしまった。
都内の高級住宅街に建つこの家は、建築家広瀬健二に惚れ込んだ上小沢夫妻が依頼して1959年に作られたもの。普通ならアパートも建ちそうな敷地の広さに、小さい平屋が佇んでいるので少し異質だ。建築家広瀬氏は当時、軽量鉄筋コンクリートによるSHと呼ばれるミニマルデザインの住宅を追究していたという。
上小沢邸においては壁のほとんどが夫妻のアイディアによってブロックになったが、塗装がされていない。縁側部分も灰色が剥き出しで、年月を経たシミもあるのだが、それがミニマルを感じさせるのかもしれない。塗装もしない、剥き出しというシンプルさがあるからだ。
おそらく、今の時代に家を建てようとする建て主も建築家も、壁をこのようにすることはまずない。雨で汚れが落ちるような最新のサイディングと呼ばれる壁材を使うか、左官の手によって壁が丁寧に仕上げられるからだ。それだけに、際立つ佇まい。
そういえば、今の私の家には庭がないけれど、コンクリの駐車スペースがあり、雰囲気は似てなくもない。いや、上小沢邸と似ていると言っているわけではなく、コーヒースタンドの駐車場と似ているかもしれないということだ。コンクリートのスペースなんて、誰も羨ましくないし、オーナーもそこについて考えることはあまりない。殺風景だから、たいていの人は少し小さな芝生スペースを作りたくなる。
だけども、ミニマリズムの佇まいを考えると、少し素敵に見えてくる。
最近、人から頂いた洒落た菓子の箱も、コーヒー豆の袋も灰色。
デザインが実にミニマルで、何か心地いい。
暖かく、有機的で色があって…もしくは緑が溢れていてというのは正しい美しさだが、コンクリ、灰色という色には、何かミニマルで「冷たい」香りがする。
冷たさを心地よく感じるかどうかは、その人次第だ。
March 1, 2020
ハイテク・ミニマリズム沼畑直樹

長い間、人々は家の中に何があるかで、自分を表現していた。
人を招き、本棚を見せ、持っているレコードやCD、映画などのコンテンツをさりげなく配置した。
1人暮らしをはじめたばかりの若者のワンルームでさえそうだった。
そこに本やCDがないということは、本や音楽に造詣がないことに直結していた。
でも今は、そこに本がなくても、その人の右手で掴まれたスレートの中にデジタル化して存在している。
部屋の中を見ただけでは、その人の興味や趣味、読んできた本や観てきた映画のヒストリーはもうわからないし、判断してはいけない。
本来なら、本で狭い部屋が埋め尽くされるような本好きの人でも、すっきりと片付いた部屋で本を読めるのが今だ。
すべてはテクノロジーのおかげ。ハイテクによって完成する、『ハイテク・ミニマリズム(Hi-tech minimalism)』だ。
エレクトリック・エイジが享受するハイテク・ミニマリズムは、部屋の中だけではない。車でも同じことが起こっている。EVカーの新ブランド、ポールスターが先日発表したコンセプトには、ハイテク・ミニマリズムのアイディアがふんだんに盛り込まれている。
「ポールスター・プリセプト」と呼ばれるコンセプトでは、周囲を把握するためのミラー等を廃して、センサーやカメラを搭載。それによって、従来は後ろの状況を把握するために必要だった窓自体の必要がなくなった。
かわりに、リアゲートの開口部を大きくすることができる。
また、運転中の視覚的ノイズを減らすためには、視線を追う機器を搭載することで、外の前方を見ているときはモニタが暗くなる。
インテリアはリサイクル素材などを使い、従来のプレミアム要素であるレーザーやウッド、クロームを使わない。それでもプレミアムを感じさせるために、デジタル的な技巧(モニタのグラフィックなど)を使う。
今までの車のインテリアは、目に見えるかたちで何かが「ある」ことがプレミアムを生み出す要素だった。「ない」と、プレミアムでも「ない」というのが現状だ。
しかし、車内全体がモニタ化、投影(マッピング)化されていくことで、デザイン要素はデジタルなグラフィックに集約されていく。電気を消した状態では、シンプルな箱しかなくなっていく可能性があるのだ。車外の風景を映し出すために、たとえばドアの内側はシンプルな表面のほうがいい。
同じように、ホテルの室内、カフェの室内、高級レストラン、オフィスと、ハイテク・ミニマリズムによって未来像が変わるものは少なくない。
高級とは何なのか。美しい空間とは何なのか。デジタル化によって生まれたハイテク・ミニマリズムが変える価値観は予測不可能だ。
February 18, 2020
使い切る楽しみ 佐々木典士

ぼくが乗っている車、ロードスターの魅力は本当にたくさんある。そのひとつは「使い切れる」というところにある。排気量は1500ccだから全然大きくも速くもない。しかし一般道では充分な加速が楽しめ、高速でもオーバースピードになりすぎる心配もあまりない。
前に乗っていた軽自動車も一般道では充分だが、高速でアクセルをずっとベタ踏みにしていても覆面パトカーに捕まらない程度のスピードしか出なかった。安全とも言えるが、この場合はちょっと足りない。
岡山国際サーキットに運転の勉強をしにいったことがあったのだが、そこで会った人はメルセデス・ベンツのAMGからロードスターに乗り換えたと言っていた。前の車では何百キロも出せたと言っていたが、それを使える機会は日本ではない(ドイツのアウトバーンとかだと話は変わる)ので買い替えたらしい。バイクも同じで大型は安定感も余裕もあるが、小排気量車はアクセルを思いっきりひねれる楽しみがある。「フルスロットルだ!」というあの感覚。
性能が高く、余裕があることにももちろん価値がある。それとは全く違うベクトルで、性能を使い切れているという感覚にも価値が宿る。ぼくはどちらかというと後者の感覚が好きなので、車は好きだが、高価な大排気量のスポーツカーを買おうとは思わない。
ミニマリストの部屋で言えば、自分の持っている持ち物が死蔵せず、有機的に活躍しているときと近い。豪邸ではなく、自分の「円」が届くような範囲の家で暮らしたい。そういうときにぼくは喜びを感じる。足りないわけでもなく、無駄も大きすぎず。自分がしたいと思うことを、自分が持っているものすべてを動員して達成している感覚。
ミニマリストの持ち物は「全員1軍でがっちりスクラムを組んでいる感じ」と表現したことがあったが、今はもう少し余裕があってもいいと思うようになった。ほぼ1軍だが、誰かが怪我をしたときのための交代要員は何人かいる、ぐらいがちょうどいいかもしれない。隠され続ける秘密兵器はなく、スポイルされる2軍3軍もそこにはいない。
ここまで書いてきて「自分」もそうだと思った。人と比べることにロクなことはないとミニマリズムを通して実感したが、それでも無意識に比べ始めたりしてしまうのが人間。環境や持って生まれた能力は確かに違うかもしれず、成し遂げられる仕事にも差はあるだろう。しかし自分に与えられたものを使い切ったと思える爽やかな満足感は、それとは独立してある。だからその満足感は誰の元へも訪れることができる。
February 14, 2020
半径5mからの環境学 なぜ鹿や猪が増えているのか? 千松信也さんに聞く 佐々木典士

近年、猪や鹿の増加による農作物の獣害について耳にする機会が増えました。京都でも2017年に平安神宮などの有名な観光地にも猪の出没が相次ぎ、たびたびニュースで話題になりました。この問題の背景を、京都の山間に暮らす猟師という目線で見つめられている千松信也さんにお聞きしました。
[image error]
千松信也(せんまつしんや)1974年兵庫生まれ。京都大学に在籍中から狩猟免許を取得し、運送業と共に猟を行っている。著作に『ぼくは猟師になった』(新潮社)、『けもの道の歩き方』(リトルモア)。最新刊は『自分の力で肉を獲る 10歳から学ぶ狩猟の世界』(旬報社)
[image error]▲京都の街中からも近く、そして家の庭からすぐに裏山に登れるという恵まれた立地のお家。まさに街と山の「間」で長年、猟を続けてこられた千松さん。
鉄砲は武士より農民が多く持っていた
──千松さんは、猪などの増加について長い時間軸でお考えになっているようですね。
たとえば江戸時代には、京都のあたりは禿山が多かったようなんですよね。当時の絵図を見てみると、草木が生えていては絶対にわからないような山の形が、正しく描かれていたりするんです。
──江戸時代と言えば自然がそのまま残っているようなイメージがあったので意外です。
京都は町の規模も大きいし、すでに禿山になるほど近くの山の木はたくさん利用されていたようです。でもそれだけ山に人が入っていたということでもあるし、そういった見晴らしのいいところは猪は本能的に避けます。でももう少し山あいの地域を見てみると、その頃から猪垣と呼ばれる石垣が作られていたり、武士より農民が持っている鉄砲の方が多かったりもして獣害対策は行われてきたんですよね。
里山で住み分けられていたというのも幻想
──獣害自体は昔からあった問題ということですね。
人間が勝手に自然を作り変えてきたことも今は裏目に出ています。明治以降は京都のような大きな町でなくても、急激な人口増加に伴って森林利用が拡大しました。そうして猪や鹿の生息域は狭められていき、戦後は乱獲もあり、その生息数も激減しました。人口が増えるに従い、建築資材としてスギ、ヒノキといった木が拡大造林政策によって植えられたのですが、奥山にあるそういった針葉樹の森は今では放置されるようになってしまいました。その森は薄暗く、動物たちの食べ物になるようなものはありません。里山には薪や炭に利用するためにドングリがなるコナラやクヌギなどを中心とした薪炭林と呼ばれる人工林がありましたが、燃料として使われなくなるにしたがってこれも伐採されず放置されるようになりました。奥山には住めないけど、里山には食べる物があるという状態で、人間が動物をおびき寄せてしまったとも言えるんですよね。また、鹿は草食動物で本来は山裾の動物なので、生息数が増えると山から出てくるのは当然です。
──鹿も猪も、人が住む近くで暮らさざるを得ない状況になってしまっているんですね。
保護政策や人間の森林利用の放棄などの影響で鹿や猪の生息数は回復し、現在は各地で獣害が大問題になっています。こう考えると山間部の農地で獣害対策をせずに農業が行えたこの100年ほどが、むしろ特殊な時代だったと言えると思います。江戸時代には狼がいましたが獣害はあった。昭和の里山は人と動物がうまく住み分けられていた時代だったというのも人間が数を一時的に減らしてしまっただけのことであって、幻想だと思います。
[image error]
[image error]▲千松さんのお家にはたくさんの生き物が飼われています。ミツバチを飼うと、熊やスズメバチが寄ってくる。鶏を飼えば、狐やアオダイショウの多さを知る。生き物を飼うことでも、身近にいる動物たちの気配を感じ取れると言います。
──京都で、人の街にまで猪が降りてきてしまっているのはなぜなんでしょうか?
猪は生息数が増えると新たな生息域を探そうとします。琵琶湖の沖島や瀬戸内海など各地で泳いでいる猪が見られたりしていますが、そうまでして新たな場所を探そうとするんですよね。そして猪が現れている箇所は、実は東山や山科といった広大な鳥獣保護区と重なります。猪は基本的にとても臆病な動物ですが、狩猟が禁止されている地域の猪だから、人に追われたり、痛い目に合わされた経験がなく、怖いとも思っていない。
[image error]▲庭から登った裏山を案内して頂きました。本当に人が住むそばで、鹿の足跡や猪の牙の跡がたくさん見つかることがわかります。
鳥獣保護区のあり方とは?
──よく猪に「襲われた」とニュースになりますが、新たに住める場所を探しているうちに街に出てしまい、混乱しているというほうが正しい認識かもしれませんね。
京都で猪が街にたくさん出始めたのは2017年以降のことなので、鳥獣保護区の中で住めるだけの猪がいよいよ飽和してきたと言えると思います。鳥獣保護区では、あらゆる動物を一律に獲ってはいけないことになっていますが、果たしてそれが、本当に自然や生態系を守ることにつながるかどうかも考えてみるべきだと思います。
──人間の手を入れないことが「自然」ではない、ともおっしゃられていますね。
里山って言われるエリアの雑木林にしても先程言ったように、すでに自然に生えている状態とは程遠い状態です。だからその歪な状態のまま自然に任せようというのは無責任ですし、それで元あった豊かな自然には戻るわけでもないと思うんです。人間がやることはいつもいろいろ間違えるし、限界があると思いますけど、それでもやはり試行錯誤を繰り返していくべきではないでしょうか。
【千松さんのおすすめ本】
武井弘一『鉄砲を手放さなかった百姓たち』(朝日新聞出版)
[image error]

多くの農民が、刀狩り以降も鉄砲を持ち、獣害対策に利用していた。昔から農民は獣害に苦慮し、戦い続けてきた歴史がわかります。
千松さんの最新刊『自分の力で肉を獲る 10歳から学ぶ狩猟の世界』(旬報社)
[image error]

Fumio Sasaki's Blog
- Fumio Sasaki's profile
- 598 followers



