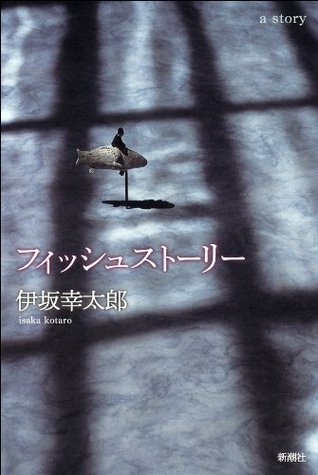More on this book
Community
Kindle Notes & Highlights
地下鉄に乗っている。最終電車近くの下り線は空いていた。両脇に妻と娘が同じような顔で眠っている。妻が握っている切符が落ちないだろうか、とそれが気になって仕方がなかった。 向かいに座っている学生たちが、二駅ほど前から車の話をしている。車内に彼らの声が響いた。 「マツダのロータリーエンジンはさ」と茶色の髪をした男が言った。 その瞬間、十年前の出来事を思い出した。「エンジン」という単語のせいだ。 もう一度、寄りかかる妻と娘の顔を窺い、その後
にはろくな灯りもない。幕に覆われたかのような暗さだ。 「気配で分かるもんだな」ベンチで隣に座る河原崎さんが、ぽつりと言った。 動物たちのことだ。なきごえがするわけでも、足音が鳴るわけでもなかったが、同じ空間に彼らがいるのは分かった。呼吸する音、鼓動の音、もしくは毛づくろいをし、姿勢を変え、羽を畳む音、そのうちのどれ、とは特定できないが、私たちの皮膚を揺らす気配がそこら中にあった。 「ああ、いますね」私はうなずく。 「あそこを見ろよ」 河原崎さんが突然、人差し指を出し、斜め先に向けた。私は首を伸ばし、目を細める。人がうつ伏せで、倒れていた。いつからそこにいたのだろうか。さ